予防歯科とは?行うことやメリット、頻度も

こんにちは。春日井市玉野町にある歯医者「くまの歯科」です。
歯が痛くなったり、何か不具合が生じたりしたときに歯医者に行くのが一般的な行動かもしれませんが、口腔トラブルは予防することが非常に重要です。
予防歯科とは、虫歯や歯周病といったトラブルが起こらないように、歯科医院や自宅でのケアを通して、健康な歯と口腔内の状態を維持していく考え方です。80歳で20本の歯を保つ8020運動なども推進され、予防意識が高まりつつあります。
この記事では、予防歯科の基本から、実際に行う内容、得られるメリット、通院の頻度、さらには自宅でできるセルフケア法まで幅広く解説していきます。
予防歯科とは

予防歯科とは、虫歯や歯周病などの口腔トラブルが起こる前に、それらを未然に防ぐための診療やケアを行う歯科医療の一分野です。従来の歯科医療では治療に重点を置いていたのに対し、予防歯科は予防・健康維持に重きを置いている点が特徴です。
定期的な歯科検診、歯石除去、フッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて、口腔内の衛生状態を良好に保ちます。
特に、日本では近年、予防歯科の考え方が広まりつつあり、厚生労働省も歯の健康を維持する取り組みとしてその重要性を訴えています。虫歯や歯周病は初期段階では自覚症状が少なく、気づいた時には進行していることが多いため、予防的アプローチが効果的とされています。
予防歯科を継続的に実施することで、将来的な歯の喪失を防ぎ、全身の健康にも良い影響を与えるのです。
予防歯科で行うこと

予防歯科では、虫歯や歯周病などのトラブルを未然に防ぎ、健康な口内環境を維持するために、さまざまな処置やサポートが行われます。歯が痛くなってから治療するのではなく、定期的なケアによって問題が起こらないようにするのが、予防歯科における基本方針です。
ここでは、予防歯科で実際に行われる主な内容を見ていきましょう。
プロによる歯のクリーニング(PMTC)
PMTCとは、歯科医師や歯科衛生士が行う、専門的な歯のクリーニングのことです。専用の器具を使い、歯の表面や歯間、歯茎の境目など、日常のブラッシングでは落としきれない汚れや歯石を丁寧に除去します。
これにより、細菌の繁殖を抑え、虫歯や歯周病のリスクを大幅に下げることができます。特に、歯周ポケットの清掃は自分では難しいため、専門的なケアが欠かせません。
フッ素塗布による歯質強化
フッ素を歯に塗布することで、歯のエナメル質を強化し、酸に対する抵抗力を高めます。これにより虫歯の予防効果が期待できます。
子どもだけではなく、大人にとっても有効な処置です。定期的に行うことで予防効果が持続しやすくなります。
ブラッシング指導
患者さま一人ひとりの歯並びや生活習慣に応じた、正しい歯磨きの方法を歯科医師や歯科衛生士が指導します。磨き残しや力の入れすぎによる歯や歯茎への負担を減らすことで、日々のセルフケアの精度を高めます。
定期検診によるトラブルの早期発見
定期的に歯科医院で口腔内をチェックすることで、虫歯や歯周病を初期の段階で見つけられます。異常が早期に見つかると簡単なケアで済む場合も多く、歯を削るなどの治療を避けられる可能性が高まります。
予防歯科のメリット

予防歯科の最大の魅力は、歯や歯茎の健康を長期的に維持し、トラブルを未然に防げる点です。予防的な取り組みを続けることで、日常生活の質が高まり、結果として医療費の軽減にもつながります。
ここでは、予防歯科を受けることで得られる主なメリットをご紹介します。
虫歯・歯周病の発症を防げる
予防歯科では、口腔内の清掃やチェックを通じて、虫歯や歯周病が発生する前の段階で原因を取り除きます。これにより、痛みや腫れなどの不快な症状を未然に防ぐことが可能となります。
重症化を避けられる
定期検診を受けていれば、もし虫歯や歯周病になったとしても早期の段階で発見されるため、軽度な処置で済むケースが多くなります。進行してから治療を始めるよりも、身体的・経済的な負担が大幅に軽減されるのです。
医療費を抑えられる
重症化してから治療する場合、通院回数が増えたり、高額な処置が必要になったりすることがあります。予防歯科によって病気を防ぐことで、医療費を抑えられるようになります。
自分の歯を長く使える
予防歯科を継続すると、自分の歯をできるだけ多く、長く保つことができます。自分の歯で食べることは、栄養吸収だけではなく、認知機能や全身の健康にも良い影響を与えます。高齢になっても食事を楽しむためには、予防が何より重要です。
予防歯科に通う頻度

予防歯科の効果を最大限に引き出すためには、定期的な通院が欠かせません。どれくらいの頻度で通えばよいのかは、年齢や口腔内の状態、生活習慣によって異なります。多くの歯科医院では、定期検診を3か月に1回程度受けることを推奨しています。
歯垢が歯石に変わりやすい期間が約3か月であること、また歯周病菌が再増殖する周期であることが理由です。
ただし、最終的な通院頻度は、歯科医師の診断に基づいて決める必要があります。一人ひとりの生活習慣や体質に合わせた予防プランを立ててもらうことで、無理なく続けられる予防ケアを実現できます。
年齢やリスクに応じた頻度の調整
虫歯や歯周病のリスクが高い人、あるいはすでに治療歴がある人は、月に1回の頻度で通う必要がある場合もあります。口腔内の状態が非常に良好な人や丁寧なセルフケアができている人は、半年に1回でも十分なこともあります。
子どもや高齢者は特に注意
成長期の子どもは、乳歯から永久歯への移行期であり、虫歯リスクが高いため、1〜2か月ごとの通院が推奨されます。また、高齢者は唾液量の減少や嚥下機能の低下により、口腔トラブルが増えやすいため、予防的な管理がより重要です。
虫歯や歯周病を予防するために自分でできること

予防歯科では歯科医院でのケアが重要ですが、同じくらい日常生活でのセルフケアも大切です。虫歯や歯周病は生活習慣と密接に関わっているため、日々の小さな意識の積み重ねが口腔内の健康を大きく左右します。
ここでは、自宅でできる具体的な予防法をいくつかご紹介します。
正しい歯磨きを習慣づける
毎日の歯磨きは、虫歯や歯周病予防の基本です。1日2回以上、食後に丁寧に磨くことが推奨されており、特に就寝前の歯磨きは口内の細菌の繁殖を抑えるために重要です。
歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも併用することで、歯と歯の間の汚れをしっかり除去できます。
食生活の見直し
糖分の多い食事や間食が多いと、虫歯菌が活発になりやすくなります。砂糖の摂取量を減らしたり食事の時間を規則正しく保ったりすると、口内のpHバランスが安定し、虫歯のリスクを下げられます。
また、噛みごたえのある食材を取り入れることで唾液の分泌も促され、自然な洗浄作用が期待できます。
唾液の働きを意識する
唾液には、口腔内の細菌を洗い流したり、酸を中和して歯の再石灰化を促したりする重要な役割があります。水分をしっかり摂取し、よく噛むことで唾液の分泌が促進されます。ガムを噛むことも効果的です。
喫煙・過度の飲酒を控える
タバコに含まれる有害物質は、歯茎の血流を悪化させ、歯周病を進行させるリスクを高めます。また、アルコールの過剰摂取も口内を乾燥させて細菌の繁殖を促進させるため、控えることが望ましいです。
ストレスコントロール
ストレスがたまると免疫力が低下し、口腔内のトラブルが起きやすくなります。適度な運動や趣味を楽しむ時間を持ち、ストレスを上手に発散することも予防の一環となります。
まとめ

予防歯科とは、歯や歯茎の健康を守るために、虫歯や歯周病が発症する前に対処する考え方と実践方法です。歯科医院での定期的なケアと、日々の丁寧なセルフケアの両輪で、将来的なトラブルのリスクを大きく減らすことが可能となります。
また、予防歯科に通うことで、重症化を防ぎ医療費の削減にもつながる点は大きなメリットです。予防歯科は一時的な処置ではなく、一生涯にわたる健康管理の一環として捉えることが重要です。
予防歯科に興味がある方は、春日井市玉野町にある歯医者「くまの歯科」にお気軽にご相談ください。
当院は、患者さまとの「対話」を何よりも大切にしながら診療にあたっています。通常の虫歯治療だけでなく、歯周病にも力を入れており、インプラントや矯正治療、ホワイトニングなども最良の治療計画を立てて最善を尽くします。

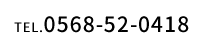
 電話をかける
電話をかける
 WEB予約
WEB予約
 アクセス
アクセス